婚姻費用とは|算定方法・請求方法
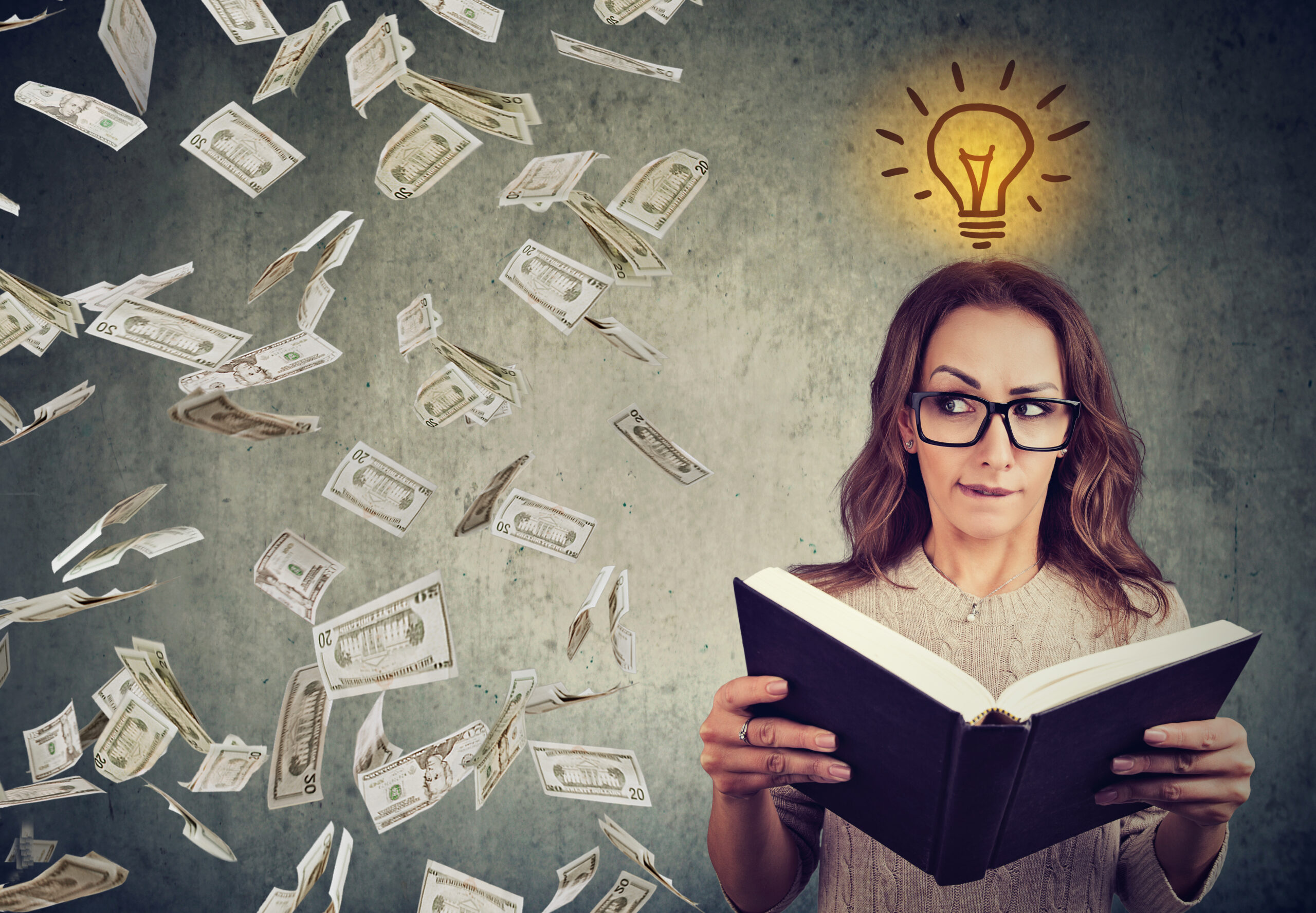
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を婚姻費用といいます。
婚姻関係にある夫婦は、互いに同居義務及び扶助義務を負っており(民法752条)、夫婦関係が円満なうちは婚姻費用について揉めることは少なく、より収入の高い方が多く負担することが一般的です。
他方で、婚姻関係が破綻して別居に至った場合などには、別居中の自分や子どもの生活費のうち一定額を相手方に請求することができます。
これを婚姻費用といいます。
本コラムでは、婚姻費用について、その算定方法・請求方法などを、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。
目次
1 婚姻費用とは
(1)婚姻費用分担請求とは
婚姻費用とは、親子間の扶助義務(民法730条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)に基づき、お互いの資産や収入などを考慮して、配偶者や子どもの生活費のうち一定額を支払うことをいいます(民法760条)。
そして、婚姻費用分担請求とは、主に別居中の場合に、この婚姻費用を相手方に請求することをいいます。
(2)婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用には,夫婦の衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
そのため、婚姻費用の使途に制限は特になく、実際に何に使ったかを相手に開示する必要もありません。
(3)養育費との違い
婚姻費用は、養育費と似ていますが、以下の点が異なります。
婚姻費用が、離婚前の配偶者と子の生活費の自己負担分を支払うものであるのに対して、養育費は、離婚後に、子の生活費のうち自己負担分を支払うものだからです。
また、養育費は、概ね18歳~大学卒業年の3月程度の年齢に達した段階で終了しますが、婚姻費用では、通常であれば終了の年齢に達した後も現に扶養に入っている子どもがいる場合、その子の生活費分を考慮することがあります。
| 誰の生活費か | どの期間が対象か | |
| 婚姻費用 | 配偶者と子の生活費 | 婚姻中 |
| 養育費 | 子の生活費 | 離婚後 |
婚姻費用を請求できるのは婚姻中と法律で定められています。ただし、同居の場合は、通常、互いの収入が一体として支出され消費されていて、生計も一体となっており、婚姻費用としての性格は不明確なので、婚姻費用だけを独立して請求することはできないことが多いです。
そのため、生計が明確に分かれている場合、すなわち通常は婚姻しているにもかかわらず別居している場合だけ、婚姻費用を請求できると理解されています。
(5)婚姻費用を請求できない場合
ア 配偶者よりも収入が著しく高い場合
自分の収入が大きく、婚姻費用の分担として自分がすべて分担すべきバランスになっているときは、婚姻費用を請求することはできません。そのような場合、自分が子どもと同居していても、収入の少ない配偶者から婚姻費用の請求を受けることがあります。
イ 権利者に別居又は破綻の原因がある場合
婚姻費用を請求する側に、不貞行為などの離婚事由に相当する別居又は婚姻関係破綻の原因がある場合には、婚姻費用を請求する自分の分の婚姻費用を請求することはできないとされています。自ら婚姻関係を破綻させておきながら婚姻費用を請求することは権利濫用に当たるからです。
ただし、その場合でも、子ども分の婚姻費用を請求することはできます。子どもは婚姻関係を破綻させた事由と無関係だからです。
なお、相手が不貞行為の事実を争っている場合や不貞行為の存在は認めつつすでに婚姻関係は破綻していたと主張される場合もあるため、不貞行為を理由に婚姻費用の請求を退けるのは必ずしも簡単ではありません。
2 婚姻費用の算定方法
(1)義務者と権利者
婚姻費用の算定方法は、具体的な夫婦の状況によって異なりますが、まず前提として夫婦の基礎収入を比較して、基礎収入の多い者が、基礎収入の少ない者、子どもを監護している者に対して、婚姻費用の支払義務を負うとされています。
婚姻費用を支払う側を義務者、婚姻費用を受け取る側を権利者と呼んでいます。
(2)婚姻費用の算定表
次に婚姻費用の金額については、裁判所が義務者と権利者の基礎収入に応じて支払うべき金額を整理したものが「簡易算定表」として裁判所のHPで公表されています。
算定表による標準的な婚姻費用額の確認方法は以下のとおりです。
①子どもの人数と年齢に応じて使用する算定表を選択します。
②選択した表の権利者及び義務者の収入欄を、給与所得者か自営業者かの区別により選びます。
③義務者の収入と権利者の収入の該当欄を交差させたところの枠内に記載されている額が標準的な婚姻費用の額となります。
(3)特別費用
婚姻費用の具体的な内容は夫婦の合意で決めることができますが、特別な費用が発生したときは、前述の簡易算定表等により算定した通常の養育費に加えて、特別費用を請求することができるとした取り決めが見られます。具体的には次のとおりです。
ア 私立学校の学費等
入学金や制服代、私立に進学した場合の学費などは、特別に支出した費用として、通常の婚姻費用に加えて請求することができる場合があります。
私立学校の学費などの請求が認められるのは、夫婦間で私立学校の学費などの負担に合意した場合、又は、夫婦の学歴や職業、資産、収入、居住地の進学状況等を考慮して、私立学校に通学することが相当と判断される場合になります。
なお、塾や習い事の月謝などの費用を特別費用として請求することは、夫婦間で合意した場合を除いて、基本的に認められません。ただし、受験塾や模試については、私立学校の費用に準じて考慮される場合もあります。
イ 住居費用
婚姻費用の支払義務者は、算定表に基づいた婚姻費用を支払うことで、権利者の住居にかかる費用を一部負担しています。そのため、基本的に、住居費用は別途特別費用として請求の対象となりません。
ただし、別居に伴う引っ越しや家賃の発生等の一部負担を求めることができる場合があります。
3 婚姻費用の支払期間
婚姻費用の支払期間は、法律上、夫婦間の扶助義務(民法752条)のある婚姻中の全期間ですが、具体的な金額は夫婦で合意しないと決まらないため、実務上、婚姻費用を請求できるのは「婚姻費用を請求したときから」とするのが一般的です。
具体的には、婚姻費用分担調停を申し立てた時点からになりますが、婚姻費用分担調停を申し立てる前に内容証明郵便や電子メール等の客観的な証拠から婚姻費用等を請求したことが明らかな場合はその請求をした時点からとすることもあります。
4 婚姻費用の請求方法
(1)話し合いによる方法
ア 夫婦間の話し合い
夫婦間で話し合って合意すれば、その時点から決められた額の婚姻費用が生じます。婚姻費用の月額、毎月の支払日、振込先口座などを具体的に決めておくと、支払がない場合に明確に督促しやすくなります。
イ 内容証明郵便の送付
夫婦間で話し合って合意ができれば良いですが、話し合いがまとまらない場合にはいつまでも婚姻費用を受け取れないことになりかねません。前述のように婚姻費用を請求できるのは婚姻費用を請求したときからなので、後日、婚姻費用を請求したことを明らかにできるように、まずは内容証明郵便等の方法により婚姻費用をした事実を客観的に明らかにしておくこともあります。
ウ 婚姻費用合意書の作成
話し合って合意に達した場合は、後で言った言わないという事態にならないように合意内容を婚姻費用合意書等の題名で文書化し、夫婦双方の記名押印を得ましょう。また、後日、合意書に従って婚姻費用を支払わなくなった場合に備えて、公正証書により合意書を作成しておくと強制執行が可能なため有効です。
(2)婚姻費用分担調停
ア 調停の申立て
夫婦間で婚姻費用について話し合ってみたが話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いに応じない場合には、当事者同士での話し合いだけでは解決が難しいものと思われます。
このような場合には婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てることになります。なお、婚姻費用分担調停を申し立てる場合、離婚についても話し合いを進めている場合が多いため同時に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる場合も多いでしょう。
イ 調停の進行
婚姻費用分担調停を申立てると、概ね1か月先に調停期日が指定され、配偶者に対して、申立書の副本と、調停期日に裁判所に来るようにとの呼出状が送られます。
調停期日では、有識者で構成される調停委員2名(男女1名ずつ)が、あなたと配偶者からそれぞれ交互に話を聞いて、婚姻費用に関する話し合いを進めます。具体的には、当事者からそれぞれ源泉徴収票などの収入資料を提出してもらい、前述の簡易算定表の金額を基準に調停委員を通じた話し合いを経て、婚姻費用に関する合意を目指すことになります。
ウ 調停の成立
調停で話し合いがまとまったときは調停が成立します。調停が成立すると、裁判官が、夫婦双方に調停条項を確認し、裁判所の調停調書に記載されます。
このとき、調停調書の正本を送達するか聞かれます。調停調書正本は、後日、相手が調停調書に記載された婚姻費用を支払わなくなった場合に、強制執行を行うのに必要な書類になります。そのため、婚姻費用の支払い等を受ける側の場合は、調停調書の正本を送達してもらいましょう。
(3)審判
調停を重ねても話し合いがまとまらなかった場合や、相手方が調停に出席せず話し合いができなかった場合は、調停は不成立となります。
調停が不成立の場合、当事者の話し合いである調停から裁判所が当事者から提出された書類や証拠を踏まえて判断を下す審判という手続に移行することになります。
審判では、裁判所が、当事者から提出された証拠等を調べ、必要性が高い場合は証人尋問を行い、婚姻費用の可否及び金額を裁判所が決定することになります。
5 婚姻費用を支払ってくれない場合の対処法(履行の確保)
(1)支払請求
調停で婚姻費用の額を取り決めたにもかかわらず婚姻費用が支払われないようであれば、まずは相手に支払うように催促することになります。
それでも相手が婚姻費用の支払に難色を示す用であれば、相手に手紙等の書面で支払を請求することが考えられます。
(2)履行勧告・履行命令
もし、このような支払請求に対して反応がなければ、裁判所から履行勧告や履行命令を行ってもらうことが考えられます。
履行勧告とは、家庭裁判所が、相手方に対し、支払を督促する手紙を送付し、通常、電話等も行ってくれる制度です。
履行命令とは、家庭裁判所が相手方に対し、一定の期間内に婚姻費用を支払うよう命令し、相手が期限を守らなければ10万円以下の過料の支払いを命じる制度です。
(3)強制執行
婚姻費用に関する調停調書や審判書、判決書があれば、法律上、強制執行することができます。なお、公正証書で作成した合意書で婚姻費用を取り決めた場合も、強制執行は認められています
具体的には、相手方の勤務先の給与を差し押さえたり、預貯金が預けてある金融機関がわかれば預貯金を差押えることができます。
6 婚姻費用の変更
婚姻費用を書面で取り決めた後は、原則として、婚姻費用の額を変更することはできませんが、婚姻費用を決めた後に著しく事情が変わったときは、婚姻費用の変更(増額または減額)を、裁判所を通じて請求することはできます。
具体的に婚姻費用の減額が認められるケースとして、給与の大幅かつ長期的な減少や、再婚して扶養家族が増えたようなケースが考えられます。
ただし、婚姻費用の変更はかなりハードルが高いため、最初に婚姻費用の額を取り決める際に、金額に十分注意する必要があります。
7 まとめ
以上のとおり、婚姻費用分担請求をどのような流れで行うかは、戦略的に考える必要があり、個別具体的な事例に応じて、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。
G&Sでは、望ましい請求時期などを踏まえて、経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて婚姻費用の請求、調停申立て等を行います。婚姻費用については、G&Sまでお気軽にご相談ください。






